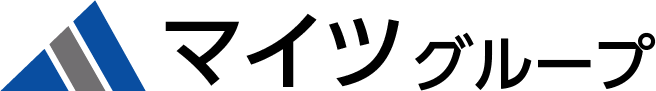PDF版はこちら →ひろよしくんのみみ 2025年8月号
~サステナブル企業を作る方法はこれだ!!~
7月20日に行われた参議院議員選挙ですが、自民党が大敗、国民民主党や参政党が大躍進し、衆参で少数与党になった自民党が今後どの様な政局運営に当たるのか、注目したいと思います。
今月号は、2017年ミツミ電機を買収したミネベアミツミをテーマに、会長兼CEOの貝沼由久氏の経営手法について学びたいと思います。
ミネベアミツミの沿革は、以下の通りです。
| 年 度 | 沿 革 |
| 1951年7月 | 東京都板橋区小豆沢において、日本初のミニチュアベアリング専門メーカー「日本ミネチュアベアリング株式会社」を設立 |
| 1960年9月 | アメリカMiniature Precision Bearings Corp.と販売提携を開始 |
| 1961年10月 | 東証二部に上場(その後一部上場を経て、プライム市場に指定替え) |
| 1968年9月 | アメリカロサンゼルスにNippon Miniature Bearing Corporationを設立。これを機にグローバル戦略を開始 |
| 1971年9月 | アメリカSKF社のREED工場を買収しアメリカでの生産拠点を確立。ミネベアの買収戦略のスタートを切る |
| 1981年10月 | 社名をミネベア株式会社に変更 |
|
2017年1月 |
ミツミ電機株式会社を株式交換方式で子会社化し、社名をミネベアミツミ株式会社に変更 |
ミネベアミツミの歴史は、ミニチュアベアリング⇒ベアリング使う極小モーターの製造⇒それらの製品を扱うメーカーへと業容を拡大してきました。
その展開をグローバルに進めるために、先代社長の高橋高見氏及び現会長兼CEOの貝沼氏もM&A戦略を採用。その実績として、貝沼氏の事業承継後、売上は6倍、営業利益は7倍超に増加させました!!
| 項目 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
| 売上高 | 978,445 | 988,424 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 |
| 税引前利益 | 58,089 | 49,527 | 90,788 | 92,128 | 75,545 |
| 売上高税引前利益率 | 5.9% | 5.0% | 8.0% | 7.1% | 5.4% |
| 総資産 | 864,481 | 976,771 | 1,104,192 | 1,299,828 | 1,416,122 |
| 総資税引前利益率 | 6.7% | 5.1% | 8.2% | 7.1% | 5.3% |
| 総資産回転率 | 1.13回 | 1.01回 | 1.02回 | 0.99回 | 0.99回 |
売上高税引前利益率は5%を超え、総資産税引前利益率(投資効率)は5~8%で推移し、メーカーとして総資産回転率も1回転をキープしており、素晴らしい会社だと思います。
貝沼氏は、事業を承継して15年間の間に、約30社の買収を行い成功させています。ミネベアミツミとニデックはM&A巧者であると言われますが、そこには経営ポリシーとの一貫性があります。
ミネベアミツミはコア事業を「8本槍」(①ベアリング、②アナログ半導体、③モーター、④アクセス製品、⑤センサー、⑥コネクタ・スイッチ、⑦電源、⑧無線・通信・ソフトウエア)と定義しています。
新たな付加価値を生み出す要件として、マーケットが大きくなくならない事、自分達の技術を生かせるニッチな領域があり、自社の製品・技術が相合出来るものである事を判断材料にしています。
相合とは、相合わせる=自社のあらゆるリソースを掛け合わせ新しい価値を創造する事を意味します。このコンセプトがシッカリしていますので、M&Aを実践する場合でもぶれないわけです。
|
買収時のチェックポイント |
価値基準 |
| 1.対象企業の製品 | 製品がグループの製品と相合するか=新たな付加価値を生み出せるか |
| 2.買収金額 | 買収金額は7年~8年で回収できるか |
| 3.立て直しの可能性 | 赤字企業を買収する場合、ミネベアミツミ傘下で立て直しが可能かどうか。工場の現場を見て判断 |
| 4.経営層の価値観 | 買収前には、ミネベアミツミの経営方針を何回も説明する会合を持ち、経営層が共鳴しているか |
そして、貝沼会長兼CEOは、経営とはサステナビリティ―であり、極端な選択と集中は間違いと説いています。
具体的事例として、2015年3月期のミネベアは携帯電話に使うLEDバックライトが絶好調で、当時最高益となる601億円(50%がLED事業利益)の利益を計上したが、今やLEDバックライトの売上はゼロになりました。
しかし、8本の事業部門で1,030億円の営業利益を計上しています。やはり、最低でも4、5事業部は持っていないと、急激な環境変化が起きた時に、企業自体が存続不能になってしまいますね。