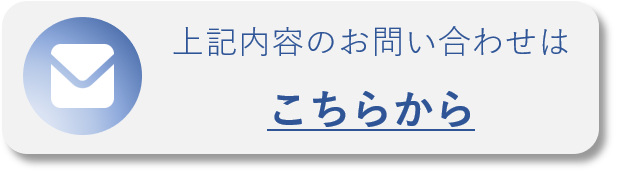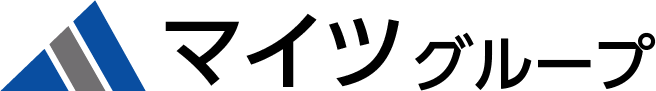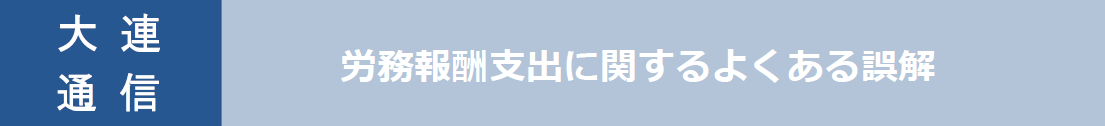
PDF版はこちら →大連通信 2025年8月号
実務上では、企業が非従業員に対して労務報酬支出(例えば、業務委託料、清掃費用、固定資産処分費用等)を支払うことが多いですが、会計税務処理に悩む会計員も少なくありません。今回、労務報酬支出に関するよくある誤解について説明します。
| 誤解 | 根拠 | リスク |
| 個人所得税を源泉徴収済みなので、発票を取得しなくても良い。 | (国家税務総局公告2018年第28号)第9条 企業が国内で発生した増値税の課税項目に該当する支出項目について、相手が税務登記の不要な組織或いは小規模零細経営業務に従事する個人の場合、その支出は税務機関が代理発行した発票又は領収書及び内部証憑を損金算入証憑とする。領収書には、領収者名称、個人氏名及び身分証明書番号、支出項目、領収金額等の関連情報を記載しなければならない。 | 企業が個人に支払う労務報酬所得(通常は発生する度)が上述の増値税徴収開始時点を超過した場合、対応する発票を取得すべきである(税務機関に発票の代理発行を申請することもできる)。さもないと、企業の当該費用支出は企業所得税法上損金不算入となる。 |
| 増値税徴収開始時点の範囲は以下の通りである。 | ||
| (1)月毎に納税する場合、月間売上は5000‐20000元(当金額を含む)。 | ||
| (2)発生する度に納税する場合、毎回(毎日)売上は300‐500元(当金額を含む)。 | ||
| 相手が発票を提供することが難しいので、直接「給与」として記帳、税務申告を行う。 | 給与、賃金所得とは、個人が非独立の個人労務活動に従事することにより取得した所得を指す。一方、労務報酬所得とは、個人が独立して各種の技能や労務を提供することにより取得した報酬を指す。両者の主な区別は、前者には雇用と被雇用の関係があるが、後者にはこういう関係がない。 | 非従業員への労務報酬支出を給与として計上することは、費用の性質を変え、企業の給与総額の計算に影響し、税務リスクが生じる。 |
| 税務局が労務報酬の発票を代理発行する際に個人所得税を徴収済みと誤解し、自身の個人所得税源泉徴収義務を怠ってしまう。 | 税務局が発票を代理発行する際に、個人所得税に関わる場合は、経営所得を取得しており且つ税務登記を行った納税者に対して、発票の備考欄に「個人所得税は納税者(発票発行者)より法に従って自主申告納付する」と統一して記載する。 | 非従業員に労務報酬を支払う際に、個人所得税の源泉徴収義務を履行することを確保しなければならいない。企業が法に従って源泉徴収を行わなかった場合、税務処罰のリスクに直面する可能性がある。 |
| 1か月内において、同じプロジェクトで個人に労務報酬を数回支払ったが、労務報酬を合算して個人所得税を源泉徴収しなかった。 | 労務報酬所得、原稿料報酬所得、特許権使用料所得について、一回性収入に該当する場合、当該収入を取得した時点を1回とし、同じプロジェクトの連続性収入に該当する場合、1か月内に取得した収入を1回とする。 | 1か月内において、同じプロジェクトで個人に支払った労務報酬は、合算して個人所得税を計算、源泉徴収すべきである。支払う度に源泉徴収を行うと、個人所得税額の正確性が損なわれる可能性がある。 |
より多くの情報を必要とされる方は、下記までお問い合わせください。