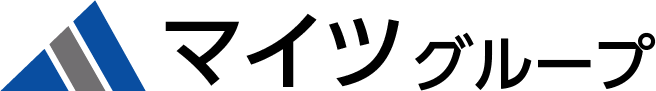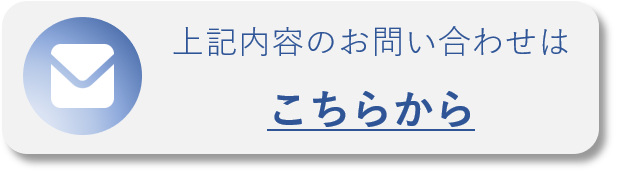![]()
ベテラン社員を活かす次世代AI人事
PDF版はこちら →人事労務通信 2025年9月号
上海の日系工場で、ベテラン中国人管理職2人が退職した。理由は「若手のAIスコアばかりが評価され、自分の貢献は見てもらえていない」から――AIで「公平な人事」を実現しようとしているはずが、逆に信頼を失う――これは、これからAI活用で公平かつ透明性の高い人事評価を行っていこうと考える企業が見落としてはならない重要な視点です。
中国では企業微信や釘釘を使った社内コミュニケーションが一般化しており、またこれらと連携したAI人事ツールも多数リリースされています。勤怠、生産性、目標達成をリアルタイム分析し、評価を自動化(データドリブン人事)できるような環境が整ってきています。
しかし、AIに限らず、過去の成果主義導入などでも同様のことがありましたが、数字に現れにくい「組織を支える力」 を無視すれば、ベテラン層の「面子」が傷つき、離職や陰の抵抗(サボタージュ)を招くリスクがあります。もちろんデータドリブン人事が悪いのではありません。データの質と、データ以外の重要な要素を欠いてしまうことが悪い。ではどうすべきでしょう。
①AIで、「日常」を可視化する
- 過去のDXと異なるAIの大きなアドバンテージが、チャット、メール、会議議事、タスク進捗表などをAIが分析し、記録を自動化してくれるという点にあります。設定された書式に従ってわざわざデータを打ち込まなくても、様々な日常活動記録から、目に見える成果だけでなく、「新人指導」「チーム支援」「トラブル対応」なども抽出することができます。(議事録、レビューメモ、面談記録等をAI化していくことが前提)こうした要素の何が評価に値するものであるかを的確に設定し、評価スコアに活用することが可能になります。
②スコアが絶対ではない
- AIによる評価は、それが「制度」として運用される以上、定量的なスコアとして事前に設定した公式で算出されることになります。これはもちろん、データドリブンをうたう上で重視されるべきものですが、それが全て、になってしまってはいけません。AIによる客観的評価を進めると同時に、「スコアとしては大した重みにならなかった」事象、記録にも残らなかった活動等の中から、別枠の表彰対象を作っていく、期初には想定していなかった評価ウェイトの偏りを、実際の貢献度に応じて是正するなど、人間が「主観で対応する」部分を必ず残してください。
③ベテラン主導で「次世代の仕組み」をつくり運用する
- では、②の人間とは誰か?経営層は可能な限りオブザーバとなり、ベテラン中国人管理職に「主導者」として参加いただくことが望まれます。本レターの以前の回でもお伝えしいる「自営型雇用組織」にも繋がりますが、AI評価の重み付けや指標選定、上記スコア外評価の対象に何を選ぶかなど、ベテランの経験と現場を預かる意欲を活かしましょう。「上から与えられた」制度運用ではなく「仲間とともに作っていく」立場で、組織と制度を動かしてもらうことが、これからの企業が成功する鍵になっていきます。
「データドリブン人事」の本当の目的は、誰もがチャンスを持てる公正な環境をつくり、それぞれの強みを発揮してもらうこと。そのためには、能力の高い中国人社員が自律的、主体的に活躍できる制度とすること――事業活動のAI化をベースに人事評価を変え、組織を変えていきたいとお考えの皆様、まずは本件ワークショップ開催から始めてみませんか?