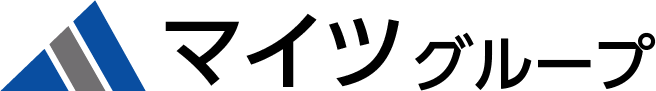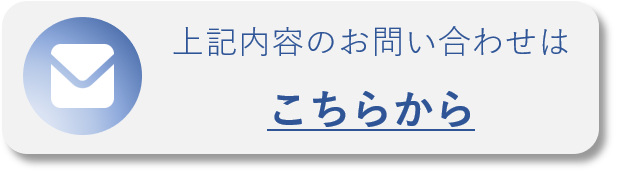![]()
PDF版はこちら →人事労務通信 2025年4月号
1.中国におけるパワハラ
私の知る限り、中国において日本のパワハラと同じ言葉はありません(セクハラはあります)。もっとも、侮辱行為が違法であることは違法であり、これを理由とした退職による経済補償金の請求も十分考えられます。今回はグループチャットにおける上司のパワハラ発言で経済補償金が発生した事例をご紹介致します。
2. 事件の概要
2017年、李さん(仮名)はある奶茶店(ミルクティー店)に入社し、勤務中の努力が認められ店長に昇進しました。2021年10月末、業務調整により李さんが勤務していた店舗が閉店し、李さんは別の店舗に異動となりました。
2021年11月2日、李さんは勤務先の変更に伴う労働契約の締結や給与、職務に関する質問を上司の張某(仮名)に対して、会社のグループチャットで相談しました。しかし、張某はこれに対しグループチャット内で李さんを繰り返し侮辱し、人格攻撃を行いました。
2021年11月5日、張某は社員を集めた会議で、李さんがグループチャット内で個人の給与に関する質問をしたことが就業規則に違反するとして、李さんを研修中のサービススタッフに降格しました。
2021年11月26日、李さんは上司からの侮辱や賃金未払いを理由に、労働仲裁を経て江蘇省南京市秦淮区人民法院に訴え、未払いの賃金の補償と労働関係解除による経済的補償金を求めました。
被告である張某は、元の奶茶店が業績不振だったため、李さんが自主的に他店舗での勤務を希望したと主張し、給与や待遇も維持されたと主張しました。また、グループチャットで給与を質問したことで、李さんは《就業規則》に定められた秘密保持のルールに違反し、意図的にトラブルを引き起こし、他の社員の業務に重大な支障をきたしたと述べました。
3. 裁判結果
秦淮区法院は審理の結果、李さんが業務調整後に自身の給与待遇について質問したことは合理的な行為であり、問題はなかったと判断しました。また、店内に詳細な給与構造が掲示されていたため、李さんは《就業規則》に違反していないと認定しました。被告の張某がグループチャット内で繰り返し侮辱や人格攻撃を行ったことは、労働者の人格尊厳を傷つけ、実質的に労働環境を損なったとみなされました。そのため、李さんは労働契約を解除する権利があると判断されました。
最終的に、裁判所は被告に対し、未払い賃金の差額と経済的補償金の支払いを命じました。
4. 専門家の見解
「中華人民共和国民法典」第109条は、自然人の人身自由と人格尊厳は法律によって保護されると規定しています。また、「中華人民共和国労働契約法」第38条第1項第1号では、使用者が労働契約に基づく労働条件を提供しなかった場合、労働者は労働契約を解除できると定めています。
本件では、使用者である張某がグループチャットで労働者の人格尊厳を著しく侮辱し、労働環境を破壊したため、労働者は労働契約を解除する権利が認められ、経済的補償金を受け取る権利があると判断されました。必ずしも上記条文には当てはまらないのですが、ひどいパワハラ行為を行った場合は適法な労働条件を提供しなかったと解釈されるということかと思います。
経済情勢により管理職や上司もイライラすることはあると思いますが、中国においてもパワハラを行わないように気をつけなければなりません。