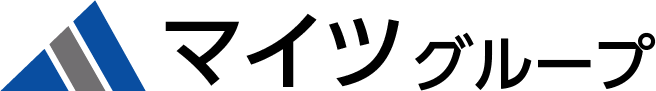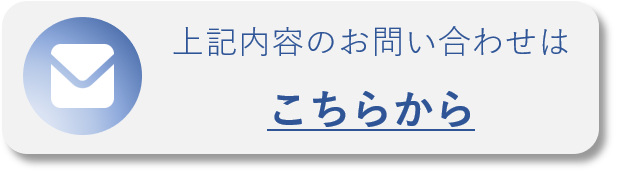![]()
社会保険の取り扱いに関する新司法解釈のポイント
PDF版はこちら →人事労務通信 2025年10月号
来たる2025年9月1日「最高人民法院の労働紛争案件の審理における法律適用問題に関する解釈(二)」(以下、「新しい司法解釈」)が施行されました。これにより、特に社会保険の取り扱いに関する企業の法的責任が、かつてなく厳格化されます。
これまで多くの企業で「従業員の同意があれば問題ない」と見なされてきた慣行や、上海市などで見られた地域独自の緩やかな運用は、もはや通用しなくなります。本レターでは、この変更部分と、企業が直面する具体的なリスク、そして施行日を前に今すぐ着手すべき対策を解説いたします。
【今回の司法解釈、何が一番変わるのか?】
結論から申し上げますと、社会保険に関するいかなる「不払いの合意」も法的に完全に無効とされる点です。新しい司法解釈第19条 は、以下の2点を明確に定めました。
結論から申し上げますと、社会保険に関するいかなる「不払いの合意」も法的に完全に無効とされる点です。新しい司法解釈第19条 は、以下の2点を明確に定めました。
1.「不払い合意」の無効
企業と従業員の間で「社会保険料を納付しない」「算定基礎額を低く抑える」といった合意書や承諾書を交わしていても、それらは全て無効となります。
企業と従業員の間で「社会保険料を納付しない」「算定基礎額を低く抑える」といった合意書や承諾書を交わしていても、それらは全て無効となります。
2.従業員からの契約解除と経済補償金の請求を「支持する」
企業による社会保険の未納の事実があれば、従業員はそれを理由に一方的に労働契約を解除し、経済補償金(退職金に相当)を請求することができ、裁判所はこれを法に基づき支持します。
これは、もはや企業の「言い分」が通用しない、極めて厳しいルールが全国で統一適用されることを意味します。
【日系企業が直面する3つの重要リスク】
この変更により、特に以下の3つのリスクが顕在化します。
この変更により、特に以下の3つのリスクが顕在化します。
リスク①:「従業員の同意」という“過去の常識”の終焉
日系企業では少ないですが、過去には多くの企業が「本人の希望で手取りを増やすため」「代わりに現金で手当を支給している」といった理由で社会保険料を収めないで雇用していました。今後は、これらは全て企業の明確な法律違反とみなされます。
日系企業では少ないですが、過去には多くの企業が「本人の希望で手取りを増やすため」「代わりに現金で手当を支給している」といった理由で社会保険料を収めないで雇用していました。今後は、これらは全て企業の明確な法律違反とみなされます。
リスク②:上海などでの「地域特有ルール」の無効化
これまで上海市などでは、企業の「悪意」がなければ、単なる社会保険料の未納だけでは従業員の経済補償金請求を認めない、比較的企業に有利な運用がなされてきました(上海市高級人民法院の「労働契約法」適用に関する若干の問題についての意見)。しかし、最高人民法院の解釈はこれに優先します。9月以降は地域に関わらず、未納付の事実だけで企業の責任が問われます。
これまで上海市などでは、企業の「悪意」がなければ、単なる社会保険料の未納だけでは従業員の経済補償金請求を認めない、比較的企業に有利な運用がなされてきました(上海市高級人民法院の「労働契約法」適用に関する若干の問題についての意見)。しかし、最高人民法院の解釈はこれに優先します。9月以降は地域に関わらず、未納付の事実だけで企業の責任が問われます。
【企業が取るべき具体的な対策】
施行まで残された時間はわずかです。「様子見」は最も危険な選択肢です。以下の対策に着手されることを推奨いたします。
施行まで残された時間はわずかです。「様子見」は最も危険な選択肢です。以下の対策に着手されることを推奨いたします。
Step 1:社会保険の納付状況の総点検と是正
まず、全従業員の社会保険料を正しく計算して納付しているか(「算定基礎額」が、各種手当を含めた「給与総額」と一致しているか等)、確認してください。実態と乖離している場合は、速やかに正しい基準に是正する必要があります。
まず、全従業員の社会保険料を正しく計算して納付しているか(「算定基礎額」が、各種手当を含めた「給与総額」と一致しているか等)、確認してください。実態と乖離している場合は、速やかに正しい基準に是正する必要があります。
Step 2:不適切な合意・慣行の即時廃止
「社会保険放棄の同意書」や「現金手当による代替支給」といった慣行は、直ちに廃止してください。これらの文書は、今後トラブルが発生した際に、むしろ企業が違法性を認識していた証拠と見なされるリスクすらあります。
「社会保険放棄の同意書」や「現金手当による代替支給」といった慣行は、直ちに廃止してください。これらの文書は、今後トラブルが発生した際に、むしろ企業が違法性を認識していた証拠と見なされるリスクすらあります。
Step 3:過去の未納分への対応方針の策定
点検の結果、過去の未納・過少納付が判明した場合、どのように対応するかを事前に検討しておくことが極めて重要です。自主的に追納するのか、それとも従業員からの請求に備えるのか。それぞれのメリット・デメリットを分析し、貴社の状況に合わせた最善の戦略を立てる必要があります。
点検の結果、過去の未納・過少納付が判明した場合、どのように対応するかを事前に検討しておくことが極めて重要です。自主的に追納するのか、それとも従業員からの請求に備えるのか。それぞれのメリット・デメリットを分析し、貴社の状況に合わせた最善の戦略を立てる必要があります。