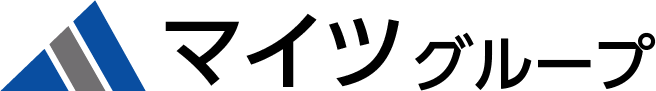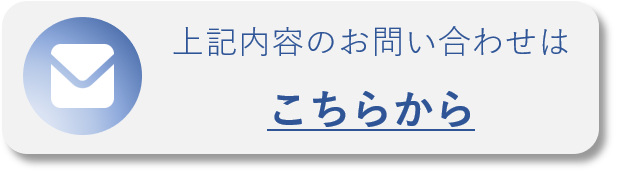PDF版はこちら →上海通信 2025年2月号
昨年は日本の税務当局による移転価格調査に対応するため、中国子会社と日本本社間の取引価格が適正であることを証明する書類を作成する機会がいくつかありました。このことから、日本税務当局による移転価格調査が増加傾向にあると感じています。
1.文書化義務導入及び国際税務の深化を背景とした移転価格調査の執行体制の変化
従来、移転価格調査は、国税局所管の資本金1億円以上の大規模企業を対象とし、国税局内の専門部署である国際調査課が専任で対応していました。しかし、2020年7月以降、移転価格専門部署が廃止され、その専門調査官が一般調査部署に配属されることで、一般調査部署でも移転価格調査を実施できる体制に変更されました。現在の移転価格調査体制は、大規模企業を対象とする国税局の調査部と、中小企業を対象とする税務署の法人課税部門で構成されています。
この体制変更の背景には、2017年に導入されたOECD BEPSプロジェクトの文書化制度の整備や国際課税制度の継続的な見直しに迅速に対応する目的があると考えられます。
2.一般法人税調査と移転価格調査の一体化
これまで移転価格調査と一般法人税調査は専門性が異なり、調査対象期間も大きく異なる(移転価格調査の方が期間は長い)ことから、基本的に別々に実施されていました。しかし、現在では両者を「一つの調査」として包括的に実施するようになっています。また、大規模企業を対象とする国税局調査が中心だった従来とは異なり、中小企業を対象とする税務署による調査が増加しています。特に、日本本社に海外子会社との関連取引に関するローカルファイルの提出を求めるケースが多く見られます。ローカルファイルを指定された期限までに提出しない場合、「推定課税」や同業者調査に基づく移転価格調査が実施される可能性があります。
3.中国子会社への影響と対応策
利益率の高い中国子会社との取引は調査の対象になりやすい傾向があります。そのため、関連会社間の移転価格が適正であることを説明する際には、利益率が高い理由が移転価格以外の要因(例:円安やエンドユーザーへの高価格販売が可能な業界特性)によるものであることを明確にする必要があります。もし説明が認められず追徴課税を受けた場合、今後の中国子会社との取引価格の見直しが求められる可能性があります。これにより、中国子会社の業績や運営管理に大きな影響が生じることも考えられます。
特に利益の大幅な減少は、中国税務当局による指摘リスクを高めるため、事前に説明文書を準備しておくことを強くお勧めします。
移転価格に関する国税庁の取組方針https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/pdf/takokuseki_01.pdf