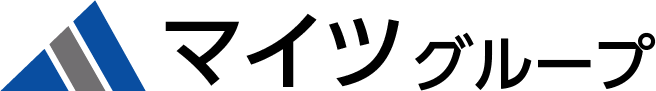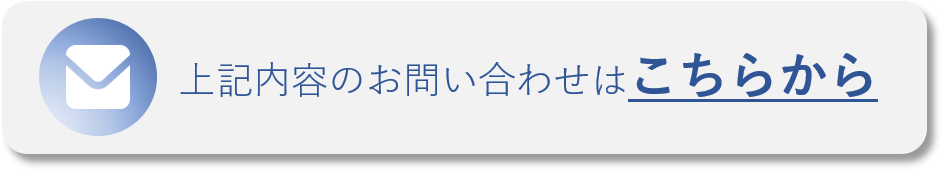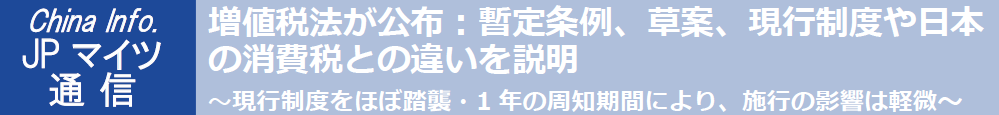
PDF版はこちら →China Info JPマイツ通信 2025年2月
増値税法(第41号)[i]が2024年12月25日付けにて公布され、2026年1月1日より施行されます。同法は、第二稿草案をほぼ踏襲し、更に建付けこそ1993年12月公布の「増値税暫定施行条例」(以下“暫定条例”と表記)[ii] が廃止され、継承的な規定となりますが、暫定条例は営業税と増値税を統合する“営改増”改革において2016年 5月の全面的適用により、実質的に現行制度に上書きされており、実務面での影響は軽微と考えられます。
従い、本稿では、同法を踏まえて増値税の基本構造の説明と共に、同法にて把握すべき事項を適宜、第二稿草案や暫定条例、現行制度、また日本の消費税と比較しつつ説明します。
| 本稿と共に、既往JPマイツ通信(【2023年11月】増値税草案(第二稿)と現行制度や日本の消費税との違いを説明/【2023年5月】中国の増値税制度と消費税インボイス制度を比較!)[iii]を併せてご参照ください。 |
1.増値税法の建付け第二稿草案[iv]に基づく重要事項
増値税法は、日本の消費税法に相当する付加価値税に係る基本法です。第一稿草案(6章・36条)➾第二稿草案(6章・37条)➾同法(6章・38条)と条項数は多くなく、また同法の施行時に廃止される規定は暫定条例のみとなっており、この点からも同法は現行制度をほぼ踏襲しつつ、一部条項の調整に止まることが分かります。
<以下、第二稿草案からの変更箇所を緑色表示>
- (1)増値税の現行の枠組みを踏襲した重要条項:以下の通りです。
税率 主要項目(抜粋、一部例外あり) 13% 貨物の販売、加工・修理などの役務提供、有形動産リース、貨物の輸入 9% 交通運輸・郵政・インフラ電信・建築・不動産リース、土地使用権の譲渡、糧食・食用植物油・水道・飼料・化学肥料・農薬・農機道具など一部商品の販売・輸入 6% 役務・無形資産の提供 3% 徴収率(簡易課税の適用税率) 0% 貨物の輸出ほか - ➤税率(第4条):貨物の販売等の基本税率は13%(役務提供は原則6%)です。右表の通り、現行税率を踏襲しています。
- ➤納税期間/期限(第30条):規定上の一納税期間は10日、15日、1か月、四半期ですが、主には現行制度と同様に、1か月(通常、一般納税人)/四半期(同、小規模納税人)を一納税期間、翌月15日を納税期限とします。
- ➤一般納税人VS小規模納税人(第8条、9条等):一般納税人は日本の課税事業者、小規模納税人は簡易課税事業者に近く、小規模納税人は“基準となる年間課税売上高を500万元以下”とし、もし“健全な会計制度等を有すれば一般納税人の登記が可能”、一般納税人はそれ以外(すなわち同売上高500万元超であれば必須)との建付けです(第9条、草案から変更無し)。
原則、前者は日本の消費税インボイス制度と同様に“増値税額=売上税額―仕入税額”、後者は簡易課税方式を選択する場合は“増値税額=販売額×徴収率”となります。簡易課税方式の場合、税率は低いものの、仕入税額控除が認められない為、ビジネスモデルに従い、慎重に判断します。 - ➤繰越税金(仕入増値税の控除留保還付金額)の還付制度(第21条):日本の消費税では、仕入(仮払)消費税額が売上(仮受)税額を上回る場合や輸出免税が発生する場合、一定の要件に該当すれば仕入消費税に対する還付を受けることが可能です。一方、中国では輸出(に対しては免税ではなくゼロ税率)に対応する仕入増値税の還付制度を除けば、期末時に“売上増値税額<仕入増値税額”でも還付が認められず翌期に繰越していましたが、2019年以降、製造業や小型薄利企業に対し留保増値税をも含む還付政策が発表され、その後、対象範囲が拡大されています[v]。
増値税法では第二稿草案をほぼ踏襲し、“業種や規模を問わず、納税人が当該増値税を翌期以降に留保するか、還付申請するかを(日本と同様に)、国務院規定に照らし選択可能”としています。 - ➤クロスボーダー役務提供時の取扱い(第4条):日本の消費税とは最も大きな差異ともいえる条項です。消費税では、海外事業者が提供する役務は原則、不課税取引[vi]となりますが、増値税では役務・無形資産取引の販売側、購入側のいずれかが中国国内にいれば原則、課税対象取引となります。則ち、当該課税取引とは下表の通りであり、日本企業など海外事業者が中国企業に役務提供時にも、提供役務が中国国内で費消される限り、課税取引となります。
-
【中国国内で発生する課税取引の定義(第4条)】① 貨物販売:貨物の発送地或いは所在地が国内② 不動産等の販売或いはリース:不動産等の所在地が国内③ 金融商品の販売:金融商品を国内で発行する場合、或いは販売者が国内単位と個人④ 本条第二項、第三項の規定以外の役務や無形資産の販売:役務、無形資産が国内で費消、或いは販売者が国内単位と個人*橙字体は、第一稿草案から第二稿草案時に変更された箇所。同法の当該箇所は、第二草案からの変更無し。
- (2)増値税の現行の枠組みから変更が生じる項目:変更項目は少ないものの、以下等が挙げられます。
-
- ➤看做し販売取引(第5条):現行制度からの大幅な変更点として、以下の通り、代理販売や総公司と分公司間の取引等、看做し販売取引の範囲が(以下、赤字の通り)大幅に削除、項目調整されています。
-
現行(暫定条例実施細則) 増値税法 ① 物品をその他単位或いは個人に引渡し代理販売(させる)② 物品の販売、代理販売③ 二つ以上の機構を設置し統一計算する納税人が、物品を一機構から他の機構に移送し販売に使用(後略)④ 自家生産或いは委託加工の物品を非増値税課税項目に使用⑤ 自家生産、委託加工の物品を集団福利或いは個人消費に使用⑥ 自家生産、委託加工或いは購入物品を、投資として他の単位或いは個人商工事業者に提供⑦ 自家生産、委託加工或いは購入物品を、株主或いは投資家に分配⑧ 自家生産、委託加工或いは購入物品を、無償にて他の単位又或いは個人に贈与① 組織単位及び個人商工事業者が自ら生産した又は委託加工した物品を集団福利厚生又は個人消費に使用する取引② 組織単位及び個人商工事業者が物品を無償譲渡する取引③ 組織単位及び個人が無形資産、不動産又は金融商品を無償譲渡する取引④ 国務院の財政、税務所轄部門が規定するその他取引*橙字体は、第一稿草案から第二稿草案時に変更された箇所、緑色表記(取消線)は、第二稿草案から同法公布時に変更された箇所
-
- ➤外税方式の表記を要求(第17条):現行制度では、取引金額に内税(増値税額込み)か、外税(増値税額別)かの明記が無い場合、増値税は内税扱いですが、同法(草案を含む)では、“増値税は外税とし、課税取引の販売価格には増値税の税額を含まない“と定めており、注意が必要です[vii]。
2.留意事項
増値税法は2026年1月施行と周知期間が約1年もある上、現行の枠組みをほぼ踏襲しており、施行による混乱等は生じ得ないものと考えます。但し、一部項目(留保増値税の還付制度等)のように国務院(等で)の規定に照らすとの記述や、今後の実施細則を始めとする各種の補充規定の公布を鑑み、引続き、情報収集に留意しつつ、適切に対応すべきと考えます。
[i] 原文URL:中华人民共和国增值税法__中国政府网
[ii] 2009年1月1日改正施行の原文URL:中华人民共和国增值税暂行条例 (chinatax.gov.cn)
[iii]マイツグループのニューズレターは右記URLの通り。URL:ニューズレター アーカイブ| 株式会社マイツ
[iv] 原文URL: http://www.npc.gov.cn/flcaw/flca/ff8081818a1cb546018a49c4930940cf/attachment.pdf
[v] 財政部・国家税務総局公告2022年14号、同第21号及びJPマイツ通信(2022年4月)等を参照のこと。
[vi] 例外として、”リバースチャージ方式”がある。URL: 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁 (nta.go.jp)
[vii] 日本では積上げ計算(外税扱い)と割戻し計算(内税扱い)のいずれも可。下記URL等を参照のこと
URL:No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁 (nta.go.jp)